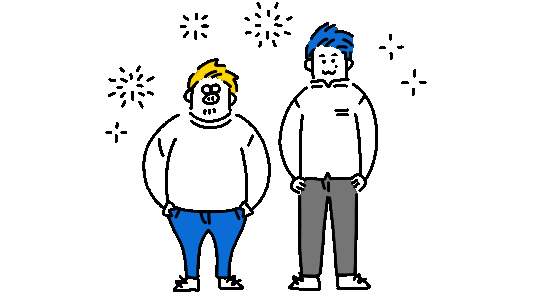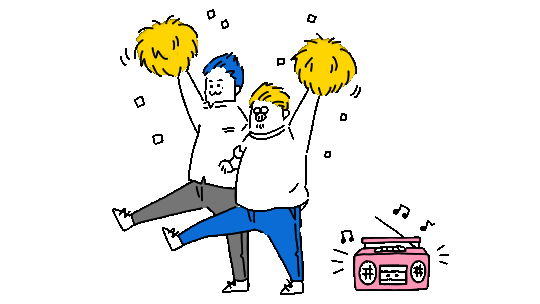遠山貴一のAI勉強日記|第7話 マーケティング篇 完結編~AIと一緒に1年走ってわかった「本当に大事なこと」~
このブログは、**「宮崎の経営者が”へー!こんな使い方ならウチでもできそう”と感じてAIに触れるきっかけになること」を願って、ハナビヤが実践するAI導入のリアルを記録しているものです。最後に分析結果を元に俯瞰で見た未来とハナビヤの経営計画発表会で出した一部を公開します。
AIマーケティングシリーズで得た「2つの財産」
1. 自社の「当たり前」が武器だとわかった
PEST、SWOT、3C、STP、ペルソナ…いろんなフレームワークをAIと一緒にやってきて気づいたのは、**「うちの強みは個人スキルに依存していた」**ということ。
例えば:
- 雑談の中でお客さんの本当の悩みや課題を見つけ出すこと
- 「こんな感じ」という曖昧な要望を形にできる翻訳力
- 納品後も定期的に連絡を取り続ける関係性
これ、他の会社もやってるところはある。でも、うちが武器として成立していたのはスタッフの個人スキルが高いからだった。ただ、新人が入ってきたときに「見て覚えろ」じゃダメなんです。だから、これを可視化することにしました。社内に**「ある仕組み」**を導入して、各部で運用してもらうことで教科書を作っていく。そんな取り組みを始めています。
2. 属人化の正体が見えた
「遠山さんがいい」「この担当者じゃないと」と言われることが多かったんですが、AIと対話することで「何が属人的なのか」が明確になったんです。
実は技術じゃなくて:
- 話の聞き方のパターン
- 質問を投げかけるタイミング
- 提案の組み立て方
これらの「暗黙知」を言語化できたことで、今後は仕組み化していけそうです。まだマニュアル化まではできてないけど、前述の**「ある仕組み」**の中へ導入していく道筋は見えてきました。
実際に起きた変化(現場のリアル)
作業時間が激減、考える時間が激増
提案書の下書きやプレゼンシートの構成をAIに任せるようになって、効率が劇的に変わりました。新人スタッフだと、提案書作成に1-2日かかることもある。でも、AIでたたき台を15分で作って、半日である程度形にできるようになった。浮いた時間で何ができるか?俯瞰で見て修正したり、ロールプレイの時間に充てたり。作業に追われるんじゃなくて、質を高める時間が確保できるようになったんです。
日程調整の自動化で生まれた余白
1人の日程調整なら大した時間じゃない。でも、うちはチームで動くことが多いから、4-5人の日程を調整してクライアントへ候補日を出すのにめちゃくちゃ時間がかかってた。これまでTime Rexやアイテマスとかのツールを使ってたけど、コストがかかる。そこでClaude MCPとGoogleカレンダーを連携させたら、日程候補を瞬時に出して、リクエストまで送れるようになった。
例えば、僕が出席する全社員面談(25人分)の日程を瞬時に打ち返してくれて、面談者にリクエストを送り、先方が「はい」を押せば終了。これだけで、年間36万円のコストカットに繋がりました。
データを俯瞰して見る目が養われた
一番大きな変化は、プレゼン前にデータをAIで洗い出して、全体を俯瞰できるようになったこと。例えば、お客さんの業界データ、競合の動向、過去の似た案件…これらを一気に整理してもらうと、**「あ、ここが課題だな」**というポイントがすぐ見えるようになった。このスキルと選球眼を可視化し、後輩に教える仕組みが必要だと感じた。勘を可視化することがAIによって可能になるのではないかと考えています。
AIとの向き合い方:1年でわかった重要なポイント
ポイント1:内容を理解してから作業させる
最近よく見かけるのが、AIで調べたり分析したものをそのまま提出してくること。
「これ、AIが出した分析です」
って持ってくるんだけど、中身を聞いてみると本人が理解してないことがある。これじゃダメなんです。
AIは優秀なアシスタントだけど、最終的に判断するのは人間。だから、AIが出した結果を一度自分の頭で咀嚼して、理解した上で使うことが大事。
ポイント2:ソース元の確認は必須
AIはよく間違えます。なんならChatGPTの数字系はマジでダメ。
うちはMFクラウド会計とChatGPTをAPIで繋いでいて、財務分析や当月の良い点悪い点を分析させてるけど、細かい数字を間違えがち。おおよそが合ってるから参考程度には使えるけど、PLは必ず確認しなくてはならない。
マーケティングでも同じ。例えば「宮崎県の企業数」とか聞いても、いつのデータなのか、どこから引用したのかを確認しないと、古い情報や間違った数字を平気で出してくる。
だから、ディープリサーチをかけるときも、ChatGPTとClaudeで両方洗い出してソース元も確認するようにしています。特にプレゼン資料で使うときは、ウソになっちゃうから要注意です。
ポイント3:複数のAIで検証する習慣
これ、めちゃくちゃ大事。1つのAIだけに依存しちゃダメです。
同じ質問をChatGPTとClaudeに投げると、違う答えが返ってくることがよくある。それぞれ得意分野が違うから当然なんだけど、この違いを見比べることで、より正確な分析ができるようになります。
宮崎の経営者の皆さんへ:これからAIを始めるなら
1年AIと付き合ってきて思うのは、AIは分析したり作業を代わりにやってくれるツールだということ。
壁打ちをする際には要注意。AIはいいことしか言ってくれないから、マジで気をつけないといけない。
AIの本当の価値
孤独な意思決定の相談相手 社長って、相談できる相手が少ないじゃないですか。AIなら夜中でも早朝でも付き合ってくれる。ただし、批判的な意見は期待しちゃダメ。
実践的なアドバイス
まず無料版から始めてOK ChatGPTもClaudeも無料版があります。まずはそこから。「AIと会話する」ことに慣れるのが第一歩。
完璧を求めない 最初は「天気どう?」くらいから始めていいんです。失敗しても誰も困りません。むしろ「なんでこんな答えが出たんだろう?」と考えることが学びになります。
ハナビヤが実際に課金して使っているAI
参考までに、うちが社内で導入しているAIツールを紹介します
基本の対話AI
- ChatGPT Pro:プレゼン資料や企画書の下書き
- Claude MAX:深い分析や感情面の理解が必要な案件
開発・制作系
- Claude Code:コード生成や技術的な相談
- Cursor :開発チームの効率化
- Relume:Webデザインのワイヤーを組むのに便利
クリエイティブ系
- Midjourney:ビジュアルアイデアの発想支援
- Veo3:動画制作の実験的な取り組み
業務効率化
- Circleback:会議の議事録自動作成
- Genspark:リサーチや情報収集、プレゼン資料作成の効率化
- Gamma:プレゼンテーションの自動生成
最初から全部使う必要はないです。まずは無料版で慣れて、必要に応じて有料版を検討すればOK。
ハナビヤの未来戦略:AIで見えた「生き残りの道」
実は、このAI勉強日記を書きながら、ハナビヤの未来についても真剣に分析してきました。
制作業界に迫る「AIの波」
2025年、AIの進化は加速度的に進んでいます:
- 動画制作:自動編集、エフェクト生成が当たり前に
- デザイン制作:チラシ、バナー、ロゴの自動生成が可能に
- コード生成:Webサイト、アプリケーションが自動で構築される時代
正直に言うと、従来型の制作業務は大幅減少の危機にあります。
ハナビヤの脆弱性を直視する
分析して見えてきた根本的な問題。それは、うちの仕事が**「フロント側」に偏重**していること。
フロント側サービス(お客様から見える部分):
- 動画制作
- デザイン制作
- HP制作
これらはAIに代替されやすい領域なんです。
じゃあ、どうするか?
「単純制作」から「価値創造」へのシフト
こちらの具体的内容は社外秘なので割愛。
人間にしかできない価値とは?
AIがどんなに進化しても、絶対に代替できないものがある:
- クライアントの本質的課題発見(雑談から見つけ出す、あの感じ)
- 感情に訴えるストーリー作り(データじゃない、心を動かす何か)
- 責任を持った意思決定(最後は人が決める)
- 信頼関係の構築(これは絶対に人間の仕事)
クリエイターの本質的な仕事は**「視覚から脳を揺らし、感情を揺さぶること」。 AEの本質的な仕事は「クライアントと対話をし、ハナビヤの信頼を作ること」**。
これはAIには絶対にできない。
実はこの分析を元に各部門の具体的な進化戦略を経営計画発表会で話しました。
結論:AIを「脅威」ではなく「部下」として
AIを恐れるんじゃなくて、優秀な部下として活用する。そして、スタッフは**「人との対話」**に集中する。
これがハナビヤが2025年以降も生き残り、成長するための道だと確信しています。
一緒にAI活用を探求しませんか?
このシリーズを読んで「うちでもやってみたい」と思った宮崎の経営者の方、ぜひ情報交換しましょう。
失敗談も成功談も、みんなでシェアすれば、宮崎全体のレベルアップに繋がるはず。
AIは難しくない。ただ、一緒に考えてくれる相棒を得るだけ。
その一歩を踏み出すきっかけに、このブログがなれたら嬉しいです。
次回もお楽しみに!
遠山貴一のAI勉強日記シリーズ
遠山貴一のAI勉強日記シリーズ【シリーズナビゲーション】
- 📝 第1話:はじめに~AIって仕事にどう落とし込めばいいんじゃー!!
- 📝 第2話:RAGをハナビヤ流に作ったら、AIのウソが減った話
- 📝 第3話:claude MCPでkintoneやGA4など社内ツールに繋げた活用話
- 📝 第4話:マーケティング篇#1~フレームワークで会社の健康診断をしてみる話~
- 📝 第5話:マーケティング篇#2 3C分析をAIと一緒にやってみたら、”うちにしかできない役割”が浮かび上がってきた話~
- 📝 第6話:STP分析とペルソナ制作
- 📌 第7話:マーケティング篇 完結編~AIと一緒に1年走ってわかった「本当に大事なこと」~(現在の記事)
次回シリーズ「AI×クリエイティブ編」もお楽しみに!